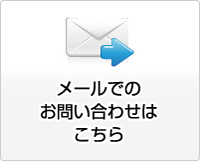- トップ
- ブログ

2024年07月24日
2024年夏季休業日のお知らせ
お客様、お取引様各位
時下、皆様にはご清祥のことと、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
大変勝手ながら、弊社夏季休業日を下記の通りとさせて戴きます。
何卒、宜しくご承知置き下さいます様、お願い申し上げます。
【記】
本社
2024年8月10日~8月18日
平塚支社
2024年8月10日~8月18日
三重支社
2024年8月10日~8月18日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- 2025.4.23
GW休業日のお知らせ - 2024.12.11
年末年始休業日のご連絡 - 2024.9.5
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づく取引適正化について - 2024.7.24
2024年夏季休業日のお知らせ - 2023.10.18
11月度休業日のお知らせ